![]()
村山格の場合
監視カメラが一斉に切れたのは深夜2時35分すぎだった。仕方なく見回りに出ることにした。当直はひとりだけだったから巡回をやったことにすることもできた。真面目すぎる性格だと自分でも思う。小さな印刷会社を勤め上げて再就職した警備会社で私はかなり重宝された。この性格のおかげだ。懐中電灯の明かりをチェックして一番上の15階から回る。エレベーターは何事もなく動いた。どのフロアもセキュリティはきちんと作動していた。問題は地下だ。この地下には公表はされていないがチームの本拠地がある。何重もある重いドアの奥には捕獲した悪魔を解剖研究する部屋があるという噂があった。私は一番手前のドアのロックがされているかを見るだけ、が仕事だった。それだけでよかったはずだった。すると、ドアの奥から聞いたこともない声がした。鳥の鳴き声のように聞こえた。獣の断末魔のようにも聞こえた。悪魔が解剖されているのか?好奇心をおさえることができなかった。ドアに耳をあてる。何も聞こえない。私は周囲を一度見回してドアのノブに手をかけた。いつもだと動くはずのない固いノブが下にカタンとさがった。気圧が変わった。空気がすっーとなかに引き込まれるのがわかった。気温が下がった。なのに背中に一筋汗が流れた。ドアをさらに数センチあけた。闇が私の体を包み込んで次のドアの前に立たせた。ドアに耳をあてる。男の声がした。
「まさか妖鳥シレーヌほどの悪魔をコントロールしていたとはな」
青柳だ。あの有名人だ。誰と話をしているんだ。
「お前は何をしようとしている」
かすれた声がする。男か?
「ふふふ」
「なぜ笑う」
「私は何もしていない。わからないのか」
「どういうことだ」
「人間が人間を殺しているだけじゃないか。勝手に滅びようとしているだけだ。私は何もしていない。人間が悪魔だ」
「そうしむけたのはお前だ」
「私がやらなくても奴らは同じことをする」
「人間じゃないみたいな言い方だな」
「歴史に学ばないからこうなるんだ」
「お前は何者だ」
「どうでもいいことだ」
「お前は何をしようとしている」
「知りたいか」
奇妙なことに相手の男の声はときどき女の声になった。そして絞るように喋っていた。青柳がその男だか女だかを殺そうとしている画が頭のなかに浮かんだ。
「まもなくどこかの国がどこかの国を攻撃するだろう。おそらく何も信じられなくなった人間どもを誰かがその国は悪魔に支配されていると断定して、正義のための防衛だと言ってボタンを押すだろう。そしてこんどはその攻撃を悪魔の仕業と言う奴が現れる。そしてまた誰かがもうひとつの正義を持ち出してボタンを押す。そして世界は終わる。終わらせるのは悪魔じゃない。人間だ」
「お前は何者だ」
「知りたいか」
ほんの少しの沈黙があった。そして奇妙な音がした。骨がさけるような。肉が破れるような。聞いていられなかった。ドアから耳を離してそこから出ようと思った。後ろのドアまで慌てて戻った。靴が滑った。転んだ。手をついたら床が濡れていた。なんだ。親指で他の指の腹のあたりをさわった。すぐにわかった。血だ。床を凝視した。そこに女の死体があった。声がでなかった。腰がぬけた。
「サタンか。お前はサタンなのか」
「どう思ってもいいさ」
「人間を滅ぼすのはやめろ」
「人間が勝手に滅びていくだけだ」
「許さない」
「許し?そんなものは最初から必要ない。人間に守るべき価値なんかない。見ればわかるだろう。自分以外のものを疑う気持ちの強さ。自分の小さな正義の心を満たすために相手を踏みにじる奴らの醜さ」
「ちがう」
「違わない」
「ちがう」
「違わない」
「ちがう」
「なぜだかわかるか。こんなにも血は美しいのは。こんなにも絶望が美しいのは。なぜ悪はなくならないのか。なぜ正義は悪を叩いていいのか。なぜそれでも悪は心を魅了するのか」
「ちがう」
「人間が悪魔だ」
「ちがう」
「不良品め」
青柳だった何かが、男だか女だかわからない何かを喰いちぎるような音がした。
「そこにいる人間よ」
妙に静かな声が響いた。そしてドアが勝手に開いた。そこにはたくさんの顔をもった大きな生き物がいた。鳥のようにも見えた。豚のようにも見えた。亀のようにも見えた。恐竜のようにも見えた。いくつもの生物の集合体のように見えた。サタンと言っていたのはこいつのことか。なんて大きさだ。
「頭でわかろうとするな。お前にはこれがどう見える?」
そういってその生き物はたくさんある右手のひとつを持ち上げた。その手は翼の生えた何かの頭を逆さまに持っていた。顔に黒い痣があった。そしてそのまままるで盃のようにその首の切れ目に口をつけて生き血を飲んだ。生温かい音がした。小さな骨が砕けるような音がした。そしてモナカか何かみたいにその顔を喰った。血まみれの顔でそいつは笑った。
「美しいだろ」
意識が朦朧とする。目の前にあるものが薄くなる。音が遠くなる。
「もうじき人間はいなくなる。そうすればこの世界はようやく私たちのものになる」
嫌な笑い声だ。そう思いながら私は気絶した。
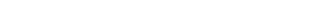




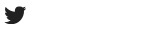


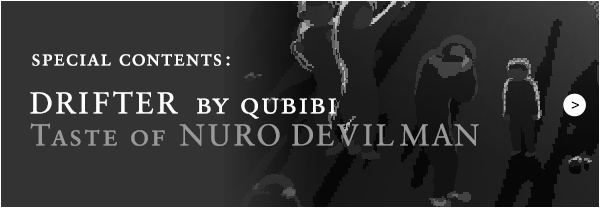
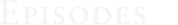
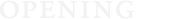
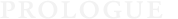
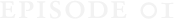
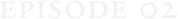






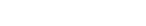

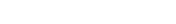




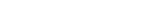
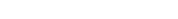



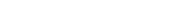


 episode 11
episode 11