![]()
友原裕貴の場合
何度も電話をしたけれど、青柳は出なかった。無理もないか。去年30万借りたまま返済の約束を守りもせず、それから一度も連絡してないからな。それでももう一度リダイヤルした。正確に言うと目の前の圧に耐えられずにそうした。青柳は高校の同級生だった。大崎にある一流の電気メーカーに勤めている仲間の出世頭だ。大学入試の直前にあいつがやった万引きの罪を俺が被ったことがある。どうせ自分は自転車の盗難で家裁に行くことが決まっていた。だからたいしたことのないことだった。でもあいつには大きなことだったみたいだ。だからそれ以降、困ると必ず助けてくれた。今までは。さすがに呆れたか。無理もない。自分が逆の立場だったら俺みたいな貧乏神とは縁を切る。電話は留守電にもならずにただなり続けた。そして唐突に切れた。どうして俺はこんな風になったんだろう。電話を切ると目の前の上下白のトレーナーの柄の悪い男が携帯で誰かと話をしたまま身を少し乗り出した。駅前の品のいい小さな喫茶店のなかで俺たちのテーブルはあきらかに浮いていた。ただそこにいるだけで迷惑をかけているのがわかった。男は突然大きな声で電話の向こうに「ヤカラさらうど」と言った。関西弁か。きっと電話の向こうの人間は数時間後の自分だ。それだけはわかった。男は電話を切ってテーブルに置いた。
「姉ちゃん灰皿。ん?なんやこの店、禁煙かいな」
「すいません」
俺は小さな声で言った。男は妙にゆっくり話はじめた。
「50万や。返済期限すぎたわ。さてあんちゃん、どないしよ」
俺は何も言わず下を向いたままだった。仕事はない。返済のあてはない。青柳は連絡がつかない。
「一週間は無利子で貸したんやで。一週間たったら一日3千円。良心的やろ。元金だけでも全然かまへんで。うちとこも慈善事業やおまへんのや。会社ゆうもんがありまっさかい返してもらわんことには困るんや」
「金利はいくらでしたでしょうか」
俺が質問したとたんに男はキレた。
「なめとんのかっ!人の話聞いとらんのかっ!」
俺はますます小さくなった。喫茶店の空気が張りつめた。
「ヤカラさらうど!」
男がどなった。俺の心はこの緩急に完全にぶっ壊された。もうこの状態から抜け出せるなら何でもいい。どこかでそう思っていた。心のなかで重い原油のようなものが布にしみこむように広がった。男に紹介されたのは雑居ビルの5階にある小汚い消費者金融だった。認可されている気配はどこにもなかった。ここで金を借りてあの男に返す。そしてまた違う男が催促にくる。たぶん俺はまた別なところで金を借りてそいつに返す。永遠に金を借りて人に返す。そして利息だけが水風船のように膨らんでいく。いつか風船が破れる。馬鹿でもそれぐらいわかる。それでも止める方法はどこにもない。雑居ビルを出ると封筒ごと男に奪い取られた。俺はどうしてこんな風になったんだろう。心のなかが原油で一杯になった。息ができなくて俺はもがいた。道にへたりこんだ。地べたは冷たくて気持ちが良かった。目の前に看板を固定するためのブロックが転がっていた。男の後頭部を殴りつけた。まるで映画のようだった。音はなかった。男は血だらけの顔で振り返った。
「何すんじゃあ、ぼけっ」
容赦なく馬乗りになって奴の顔に何度もブロックを叩きつけた。男はそのうち抵抗しなくなった。俺は男の手から封筒を奪い返した。血だらけの封筒を持って再びエレベーターに乗った。5階まで行ってさっき俺に金を貸した男に封筒をたたきつけた。男は血だらけの封筒に目を丸くした。エレベーターの開閉ボタンを強く押すと血だらけの指がすべった。俺は泣いていた。何だこの行き止まり感は。エレベーターすら俺を思い通りの場所には連れて行ってくれないのか。世の中はなんて不公平に出来ているんだ。携帯がなった。青柳からだった。
「どうした?」
軽い声だった。
「遅いよ」
「どうした?友原?」
「もう遅いんだ」
「金か?お前、金ないならしばらくうち来いよ」
俺は泣いた。そして携帯を切って床に叩きつけた。声がした。
「復讐だ」
どこにも誰もいなかった。
「復讐だ」
その声は頭のなかからだった。
「この世界に復讐だ」
やがて俺は俺の意識の境界線を失った。それは気持ちのいい状態だった。さっきの地べたの冷たさを思い出した。俺の体を動かしているのは俺ではない何かだった。俺は少し朦朧としていればよかった。エレベーターの鏡に映った俺はもう俺じゃなかった。顔が大蛇になっていた。驚かなかった。夢なのか現実なのかわからなかった。どっちでも良かった。口をあけると大きな赤い舌があった。俺の心はもはやひとつのことしか考えられなかった。「復讐だ」頭のなかで何度もその単語が繰り返された。誰の声かはわからなかった。エレベーターを降りるとたくさんのパトカーが見えた。警察が包囲していた。そこから視覚が変わった。モノクロのスライドショーのようになった。古い戦争写真か何かのようだった。体が勝手に飛び出して驚く警官を立て続けに三人食いちぎった。気分は良かった。ずっと苦しめていたあのドロドロとした気持ちがどこにもなかった。体が軽かった。何十年ぶりだろう。自由だ。高校のとき以来かもしれない。パトカーを踏みつぶしてビルの屋上までジャンプした。意のままに体が動く。驚くほどの強さ。常識も法律も借金も追いつかないだろう。ざまあみろ。全部踏みつぶしてやる。全部食いちぎってやる。ビルの屋上から今まで俺を苦しめたウジ虫どもの町を見下ろした。なんでこんなゴミダメのような世界で何を真面目に苦しんでいたんだろう。全部踏みつぶしてやる。俺は叫んだ。地鳴りのような声が空に響いた。
「待てよ」
声がした。振り返ると黒い服を着た女がいた。顔に黒い痣があった。
「なんだ」
「可哀想なひと」
「は?」
「あんた悪魔に体をのっとられたんだよ」
俺はこの女を殺るべきだ。そうでなければ殺られる。直感した。体の表面に力をいれた。全身が硬い鱗に覆われた。どんなナイフも通らないだろう。拳でコンクリに穴があいた。俺は女に飛びかかった。女は何も抵抗しなかった。そのまま俺たちはビルの谷間に落ちた。女が俺の顔面に指を2本尽きたてた。俺は首を曲げた。その隙に女が俺の脇を蹴った。女が離れた。俺は両手を広げてのばした。腕は何メートルも伸びてビルの角を捕まえた。そして俺は空間に停止した。女は?見失った。バサっと羽のような音がした。振り返ると俺の真上にいた。そのまま俺の背中にたった。そしてもういちど2本の指をすばやく俺の目のなかに入れてきた。視界を奪われた。この女。まったく力を緩めずに指を俺の顔のなかでくっつけてそのままひきぬいた。顔に穴があいた。痛みはない。けれど力が抜けた。なんだこいつは。
「残念。あんたの弱点はさっき覚えた」
俺はそのまま地上に叩きつけたられた。パトカーの連中が恐怖した顔で遠巻きにこっちをみている。体が熱い。溶けそうだ。溶けている。下半身がなくなっている。ビルの上にあの女が見えた。何も言わずに消えた。ああ。俺はそのまま溶けた。俺はどうなるんだ。俺の殺したあいつはどうなったんだ。俺の返したあの金はどうなったんだ。青柳は今何をしているんだ。青柳に金を返せなかったことをふと悔しく思った。風が吹いた。ジュッという音がアスファルトに響いた。それが俺がこの世界で聞いた最後の音だった。
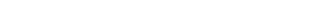




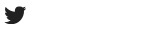


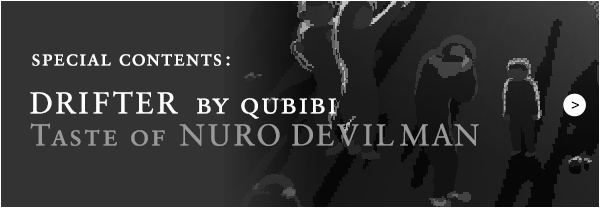
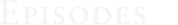
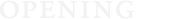
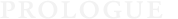
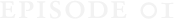
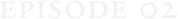






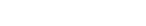

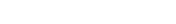




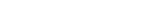
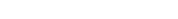



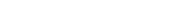


 episode 05
episode 05