![]()
稲垣光男の場合
記者という仕事が天職なのかわからない。でも体のなかにこうやって絶え間なく湧いてくる好奇心がその原動力だとしたらきっと天職なのだろう。真実を伝えたいとか、それで世界を正したいとか、そういう面倒くさい気持ちにはなったことがない。ただわからないことを知りたい。そしてそれを記事にすることでもっとあぶり出したい。記事は何かを発表する場ではなくその記事の存在によって世の中の形を変えるための道具だ。そういう道具を使っているという意識のない揚げ足とりに必死な記事は下品で嫌いだ。知っていることを全部書けばいいというものではない。世の中にどんな球を投げるべきか。それを判断するために僕たちは徹底的に知り、そして考えるべきだ。
今、この世界に何かが起こっている。そしてそれを世界は隠している。これは20年近く記者をやってきた僕の直感だ。そしてその直感はあたっていた。数カ所で頻発している変死事件。それをつなぐ横の糸が見つかった。警察はなぜか捜査本部を置かなかった。その違和感がヒントになった。どの事件に対してもだ。どれも死体が残っていなかった。警察は極秘に捜査態勢を強化していた。それは警視庁ではなく防衛省管轄の新しい組織だった。科学捜査を中心にした組織。それはほぼ戦争を意味していた。そこで何が行われようとしているのかはわからなかった。その捜査チームのなかに有名な考古学者の名前があった。飛鳥了。物理学者、科学者の名前に混じったその男の名前はとても違和感があった。八王子の奥の少し淋しい丘の中腹にその学者の家はあった。訪ねたが不在だった。大学の研究室は整理されていてとくにヒントになるようなものはなかった。少しオカルト的な研究書が目立っていたが生徒が「小説の資料みたいです」と言っていた。事件には関係がなさそうだった。そこで一枚の写真をみつけた。直感が走った。感情の一切を殺したような顔をした10才くらいの顔立ちのきれいな少女が立っていた。
「娘さん?」
「先生は結婚されていませんよ」
「じゃあこれは?」
「小説の資料じゃないですか」
生徒の目を盗んで、その写真を胸のポケットにこっそりしまった。
写真の少女の名前は、不動明。最初の変死事件の被害者の遺族だった。暗い顔は事件のせいか、元々のその子のものなのかはわからなかった。少女はもう大人になっていた。大崎の電機メーカーに勤め、祐天寺に一人暮らしをするごく普通の少し暗めの女だった。美人だったけれどその暗さゆえそれが周りに「何を考えているかわからなくて怖い」という印象を与えているようだった。会社の評価は可もなく不可もなく。尾行の甲斐のない相手だった。それでもこの暗さの奥に何かがある気がしてならなかった。ここで尾行をやめたらずっと気にしてしまいそうだった。だからしばらく続けることにした。
それから8日後、勘が当たった。聞いたことのない音が空になった。雷か。まるで神話に出てくる獣の遠吠えのような音だった。女の部屋の窓が開いた。カーテンが窓の外に向かって跳ねた。黒い何かが飛び出した。携帯がなった。デスクからだった。
「神田で変死事件だ。同じ匂いがする」
神田の駅の外れにある現場の雑居ビル一帯は封鎖されていた。たくさんのパトカーのせいで現場を確認することはできなかった。一体どうなっているのか。ふと風を感じた。ビルの屋上に何かを見た。黒い鳥のようなもの。人間か。そこに女がいた。顔に黒い痣があったがすぐに不動明だとわかった。どこか遠くを見るあの寂しげな目。でもそれは一瞬だった。黒い煙のようなものをたててすぐに女は消えた。
「話すことは何もありません」
何時間粘っても彼女はその言葉以外何ひとつ語ろうとはしなかった。でもその表情が一度だけ動いた。それはあの写真を見せたときだった。
「お父さんの事件を政府が追いかけている。どういうことだ」
僕は彼女がどう思うかわからなかったが自分の知っているすべてのこと話した。この世界に何かとんでもないことが起きようとしていることだけ感じている。それが何かわからない。方法もわからない。敵が何かもわからない。でも自分にもできることがあるはずだ。それを今やらないと後悔しそうな気がする。そう畳み掛けた。彼女は最後まで僕の話を聞いてから、ゆっくり口を開いた。
「たぶん信じないと思います」
彼女の話のほとんどは理解できなかった。悪魔がこの世界に存在している。悪魔が人間に復讐をしようとしている。悪魔は人間の心の弱さを狙ってそこを入口にこの世界に侵入しようとしている。すべてが漫画の世界にしか思えなかった。僕がそう言うと彼女は小さく笑った。
「でも父は死にました」
そうだった。実際に何人もが奇妙な死に方をしている。そしてそれを政府は隠している。そしてその政府が準備している研究体制もすべて説明がつく。記事にするには根拠が薄いが、取材を進めるには十分な根拠だった。
「真実を調べる」
僕がそう言うと彼女が小さく言った。
「分かったときはすべてが手遅れ、だったりしますよ」
そして振り返った彼女を見て僕は言葉をなくした。その顔は黒い痣に覆われていた。綺麗だなと思った。
*
記事にするべきではなかった。新聞での掲載をデスクに根拠の甘さを指摘されて見送られたあと個人の名前でブログにアップした。それがいけなかった。後悔でしばらく立ち上がれなかった。これほどまでこの世界が馬鹿だらけだとは思わなかった。ネットを中心にあの魔法陣を利用して悪魔を召喚する馬鹿が後を絶たなかった。つまるところ連中は悪魔の存在を本当は信じてはいなかった。ただのファッションだ。退屈だから。彼らのほとんどがネットにそう書き込んで儀式を実行した。そして動画をアップした。どうにも説明のつかない黒い煙のようなものに包まれてやがて人間が蛇の顔に変化する。あるものは動物と人間の混ざったようなものに。あるものは牛のような手足に。あるものは牙を。あるものは翼を。あるものは亀に。あるものは昆虫に。その動画が評判を呼んで、その召喚ゴッコはそれを禁止する政府組織によって逆に「本物じゃん、ヤバいじゃん」と拡散し続けた。誰もその流れを止められなかった。この世界がここまで腐っているとは思わなかった。連中はデビルマンになることなく、完全に悪魔にすべてを奪われた。心の弱い人間はすべてを乗っ取られる。その警告を彼らは無視した。まるでゲーム感覚だった。
「悪魔の攻撃が、ただ早まっただけですよ」
不動明は淡々としていた。そして悪魔になった連中をつぶしにでかけた。
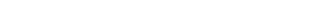




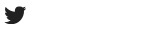


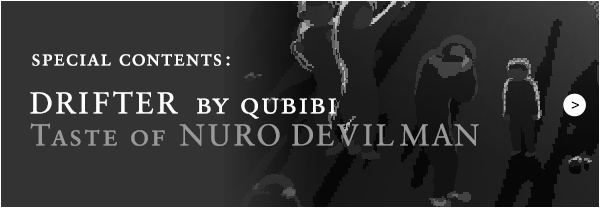
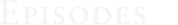
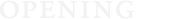
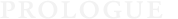
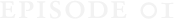
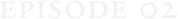






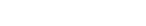

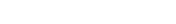




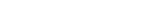
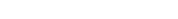



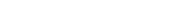


 episode 06
episode 06